子どもが本を読むのが苦手…読書の仕方が悪い?

本を読むのに苦手意識を感じるのは、読書の仕方に原因があります。たとえば、次のような読書のさせ方がその要因として挙げられます。
- 長いストーリーを読ませようとする
- 無理やり本を読ませようとする
- 親がおすすめの本を勝手に与える
読書を習慣づけるには、まず子どもが本に親しみを感じることが大切です。話が長いうえに子どもが興味のない本を読ませようとすれば、子どもは次第に読書から遠ざかります。
本を読むのが好きになり読書を習慣化させるには、子どもの興味やレベルに合わせた本の選択が必要でしょう。
本を読むことが苦手な子どもの特徴
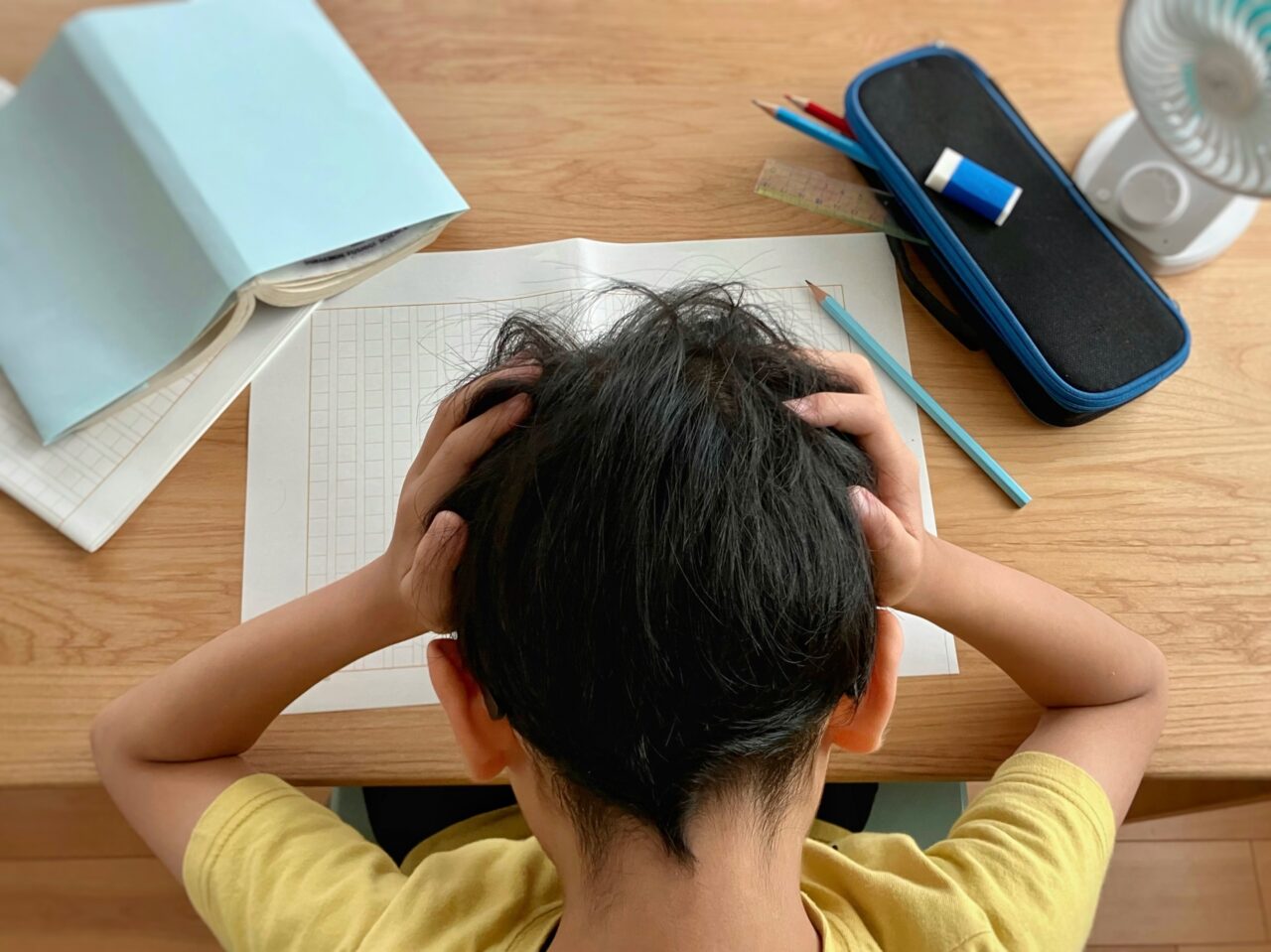
読書を習慣化させたいと思って無理やり本を与えても、子どもは本を読もうとはしないもの。読む機会をどんどん失うため、ますます習慣化は難しくなります。
親のアプローチの仕方に原因があるばかりでなく、子ども自身に読書を苦手とする特性があるのかもしれません。ここでは、本を読むのが苦手でなかなか習慣化に至らない子どもの特徴を解説します。
集中力が低い
子どもの集中力が低い場合は、読書をするのがつらくなり習慣化につながりにくいでしょう。その理由としては、本を読むのは基本的に集中力が必要で、集中しないと内容を理解できないことが挙げられます。
漫画を読む際も、テレビや動画を観たり家族の話を聞いたりしながら内容を理解するのは難しいでしょう。文字だけの本を読むとなれば、さらに集中力が必要になるものです。
周囲の雑音を一旦シャットアウトして本の世界に没頭できない子どもは、読書が苦手で本を読む習慣をつけにくいといえます。
大人しくしているのが苦手
読書をなかなか習慣化できない子どもは、どちらかといえば大人しくしているのが苦手で、動いていないと落ち着きません。
しかし、読書を習慣づけるにはある程度の忍耐強さが必要なもの。これは、椅子に座って読書ができる環境を整え、内容を理解できるまで地道に文章を追う作業が読書にあたるためです。
大人しくしているのが苦手な子どもはこの時間や状況を苦痛に感じやすいため、読書を習慣化するのが難しいと思われます。
長期的な目標設定が苦手
読書の習慣を身につけられない子どもは、長期的な目標設定が苦手です。本を読む目標の一つに最後まで読み通すことがありますが、先を見通して計画的に行動するのが苦手な子どもは、結末や結論に至るまでの過程で我慢できないこともあるでしょう。
文章の種類には最初に結論を出して理由や説明を順番に紹介する論説文もありますが、全体の要旨をとらえるためにも読み通すことが必要です。
読書は目標をもって最後まで読み切る姿勢が必要であるため、今すぐ結果を求めたり物事に流されたりする子どもは、読書を習慣づけることが難しいのだと考えられます。
勉強以外で本を読む習慣がない
学校や塾の宿題のほか多くの習い事を抱えている子どもは毎日忙しく、なかなか読書の時間をつくれません。本に触れる機会がないため自然に読書から遠ざかり、習慣化からほど遠くなるでしょう。
もちろん、勉強以外で忙しい子どものなかにも、もともと読書好きでたった5分でも本を読む習慣のある子もいます。しかし、本を読む習慣のない子どもは、そもそも読書にあまり魅力を感じず自分の本当に好きなことに時間を費やすことも多いものです。
たとえば大好きなゲームをしたり友達と遊んだりすることを優先する子の場合、読書が苦手な子どもになってしまうでしょう。
質問できる環境がない
親に「〇〇とはどういう意味なの?」と質問しても答えてもらえなかった子の場合、たとえもともと読書が好きでも、習慣化につなげられなくなってしまうケースがあります。
気軽に質問できる環境というのは、読書を習慣づけるのに効果があるのです。子どもが質問して親が「〇〇はどう思う?よくわからないなら一緒に調べよう」と提案すれば、多様なジャンルに興味を示し習慣的に本を読むようになります。
読書を習慣化させるには、知識を増やせる喜びを感じさせることも必要なのです。
読書が習慣化できている子どもの特徴
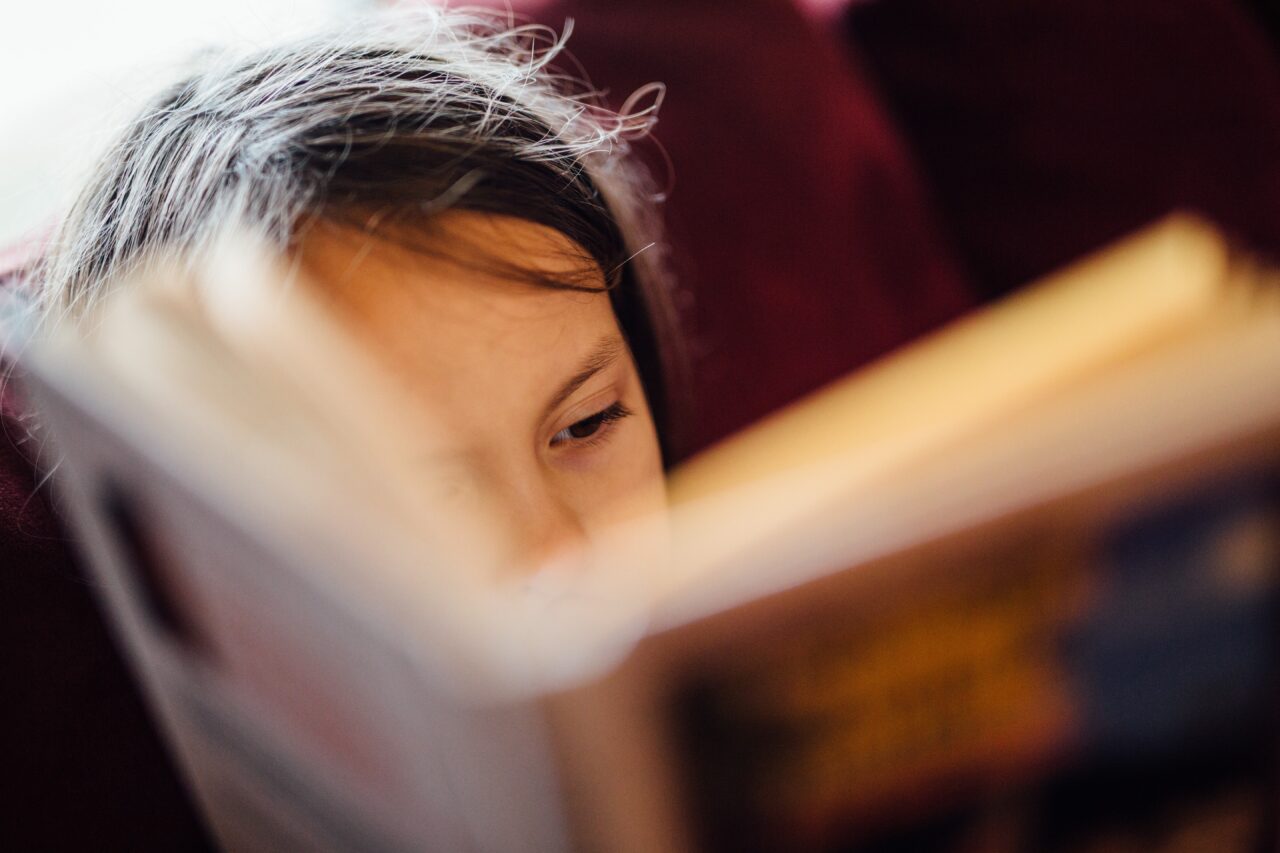
習慣的に読書するかどうかは、子どもの特徴によって変わってきます。本のなかには知的好奇心を満たす材料がそろっているため、もともと集中力や好奇心のある子どもは読書の習慣をつけやすいといえるでしょう。
ここでは、子どもに読書を好きになり読む習慣を身につけてほしいと考える親御さんに、読書が習慣化できている子どもの特徴を5つ紹介します。
本を読むタイミングが決まっている
本は、読もうと思ったらいつでもどこでも読めるものであるため、読書を習慣化させるのは簡単なように見えます。しかし、いつでもどこでも読めるからこそ、読むタイミングが重要になるのでしょう。
読書習慣のある子は、生活の中で本を読むタイミングが決まっています。たとえば、学校の朝の読書時間にあわせて「朝の支度が終わって学校に行くまでの10分」とか、「夜寝る前の10分」などと自分でタイミングを決めているのです。
タイミングを決めていると次第に習慣化されるため、おのずと本を読む時間を増やしていけるでしょう。
多くの物事に興味や関心を持っている
本を読む習慣のある子どもは、知的好奇心が高いといえるでしょう。子どもは生来、好奇心をもっているものですが、自分の疑問を親に質問して答えてもらったり一緒に調べたりすると、知的好奇心がさらに向上していきます。
知的好奇心の高い子どもは「〇〇について調べたい」と思うと、すぐに本に手を伸ばすことでしょう。わかれば楽しく、どんどん興味が広がり読書をする……。正のスパイラルが読書を習慣化させているのです。
想像力が豊か
何かになりきったり仮想世界に憧れたりする子どもはもともと想像力が高く、物語やファンタジーの世界にどっぷりつかれるでしょう。この過程が楽しいため、新しい本を探しては読みを繰り返し、読書の習慣をつけていきます。
つまり、想像力の豊かな子どもは、本の世界観を文章から感じ取れるのです。登場人物の気持ちをイメージしやすいため、あたかも自分がそうであるかのように共感できます。
言葉や文章から想像力を膨らませられるのは読書の醍醐味であり、習慣化に必要な要素といえるでしょう。
活字に抵抗感がない
読書は活字を通して、登場人物の気持ちを推測したり話の内容を整理したりする作業だといえます。そのため、活字に抵抗感がない子どもは読書の習慣がつきやすいでしょう。
一方、活字が苦手で意味の確認に時間を取られれば、読書を楽しんだり習慣化させたりするのは難しくなります。活字が苦手な子どもは、本を読む前に漢字の読みや言葉の意味を理解しなければなりません。
活字に抵抗感なく読書を楽しめるようになると、自然に本を読む習慣をつけられるのです。
読書することに義務感を感じていない
読書好きな子どもは、読書しなければならないと思っていません。「新しいことを知れるから」「読書すると楽しいから」という思いがあるから、本を読むのです。
それに対し、読書に義務感を感じてしまう子どもの場合は心の底から読書を楽しむことはできません。楽しめなければ習慣化させるのも困難になり、本を読むことから離れてしまうでしょう。
人から言われたり何かを強要されたりすることなく、自分の内側から「読書したい」と思う気持ちは、習慣化させるのに効果的なのです。







