子どものタブレット学習は効果がある?少し不安…
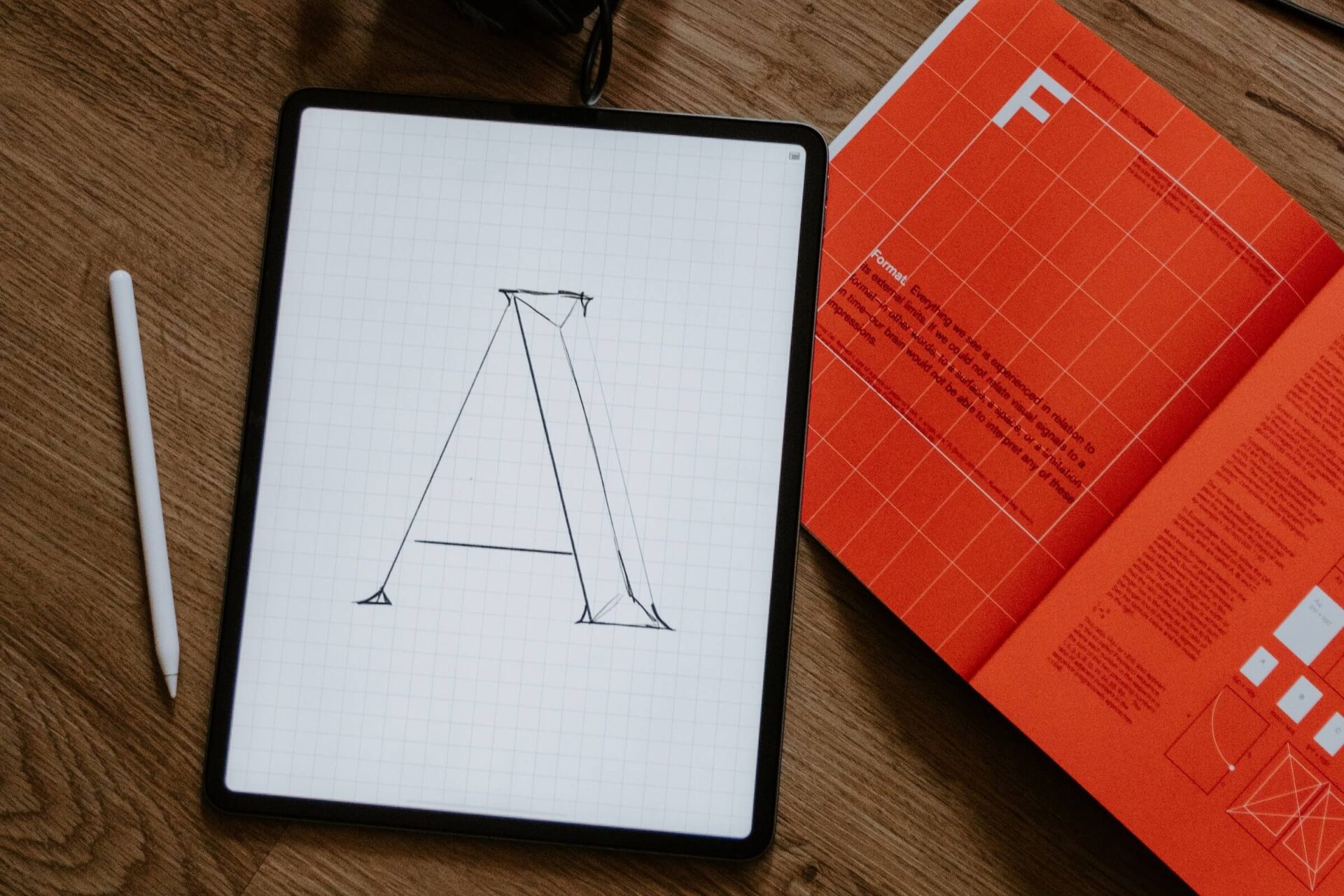
昨今の小学校では、タブレットを用いた学習が全国的に広まっています。大手携帯会社が行ったアンケートによると、小学生が学校から貸与されたタブレットの普及率は、2021年時点で46%程になっていることがわかりました。
2023年現在は、半数以上の小学生がデジタルデバイスとともに学習を行っていると予想されます。しかし、タブレット学習をしたことがない世代からすると、本当にタブレット学習が子どものためになるのかどうかと疑問を抱いてしまいますよね。
そこで今回は、子どものタブレット学習のメリット・デメリットや、スムーズな導入方法などをご紹介します。タブレット学習の利点・注意点を理解した上で、子どもに合った学習を取り入れていきましょう。
参考:NTTDocomoモバイル社会研究所「小中学生のタブレット・パソコン利用率約9割 わずか1年で約3倍に」
タブレット学習とは

タブレット学習とは、片側がタッチパネルになっているタブレット端末を活用する学習方法のことです。タブレット学習は教科名ではなく学習方法の一つであるため、特に義務教育期間で学習する科目が大きく変動することはありません。
現代の小学生は物心がついた頃からデジタルデバイスが身近にあるため、タブレットを用いての学習効果が高いと推察されます。また、タブレット端末を用いることで動画やアニメーションを通じて学習でき、楽しみながら能動的な学びを得られることが特徴です。
タブレット学習では、教科書・参考書・筆記用具などがすべてタブレット端末にインストールされている形になるため、タブレットさえ持っていればいつでもどこでも学習できる環境になります。もちろん、学習の補足として必要に応じて教材を用いることもありますが、従来の紙での学習よりも利便性が高いといえるでしょう。
小学生がタブレット学習をするメリット

ここでは、小学生がタブレット学習をするメリットについてご紹介します。タブレット学習未経験の保護者にとって、デジタルデバイスでの勉強に不安や懐疑心が生じるのは自然なことです。まずは、タブレット学習のよさについて正しく理解することから始めましょう。
時間や場所を選ばずに学べる
タブレット学習のメリットの1つは、時間や場所を選ばずに学べることです。基本的な学習教材はすべてタブレット端末にインストールされているため、ランドセルの中に重い学習道具を入れて移動する必要がありません。通学の際に忘れ物をしにくくなることも利点だといえます。
学習内容が増えても、タブレット学習であれば新しく項目をインストールすれば準備完了です。データに重量はないため、どんなに学習が進んでも荷物が増えにくいことは大きなメリットです。タブレット端末自体の持ち歩きやすさも魅力的で、家や学校に限らずいつでもどこでも学習しやすくなるでしょう。
子どもの知的好奇心を刺激するギミックが多い
子どもの知的好奇心を刺激するギミックが多いことも、タブレット学習の魅力です。タブレット学習では、アニメーション・音声・動画などを通して学べます。これは、紙の教科書や学習書には決してまねできない強みです。
子どもの学習効果を上げるためには、子ども自身が学習に能動的であることが求められます。アニメや動画などのエンタメ性が高い学習方法は、子どもの知的好奇心を刺激しやすく、学習自体に興味や関心を持つことにつながると考えられます。
子どもの学習状態が可視化されやすい
タブレット学習では子どもの学習状態が可視化されやすく、これは保護者にとっての安心材料になります。例えばタブレット端末を用いれば、自動採点機能によって問題の正解率をすぐに把握できたり、子どもの得意科目・苦手科目がリスト化したりできます。
紙での学習では、子どもがテスト用紙をなくしてしまったり、結局どこまで理解できているのかがわかりにくかったりしますよね。タブレット学習では子どもの学習の進捗がデータとして保存されるため、保護者が適切なサポートをするためのヒントになるのです。
デジタルデバイスに慣れITリテラシーが身につく
タブレット学習ではタブレットを通してデジタルデバイスに慣れるため、子どもの頃から自然にITリテラシーが身についていきます。情報のデジタル化が進む昨今では、社会で活躍するためには一定基準のIT知識やリテラシーを身につけておくことが必要です。
学習を通してタブレットをはじめとするデジタル機器や情報技術に親しむことで、ITに苦手意識を持ちにくくなり、新しい情報をスムーズに受け入れられるようになるでしょう。情報技術は今後も進化し続けることが予想されるため、タブレット学習は子どもの将来の可能性を広げるためのツールになります。
小学生がタブレット学習をするデメリット

ここでは、小学生がタブレット学習をするデメリットについてご紹介します。利便性が高いタブレット学習ですが、習慣や方法が変化すると、新たな不安も発生します。タブレット学習のネガティブな特徴も学びながら、円滑な導入方法を検討していきましょう。
遊びの道具になりやすい
小学生にとってタブレットは、学習よりも遊びの道具として認識されやすいものです。学校から支給されるタブレットには学習システムのみが導入されている場合がほとんどですが、家庭でタブレット学習を導入する場合は扱い方に注意が必要です。
「子どもが一生懸命勉強している」と思っていたら、実はゲームをしていただけだったというケースもあるでしょう。特に勉強が嫌い・苦手な子どもにとって、欲求を自制して学ぶことは難しいといえます。事前にシステムや利用に制限をかけ、正しく活用できるようにする必要があるでしょう。
学習の進捗がデバイスやシステムに依存する
タブレット学習では、学習の進捗がデバイスやシステムに依存するという特徴があります。例えば、子どもが学習に興味を持って「もっと色々なことを勉強したい」と思っても、タブレット学習のみでは機能に限界がある可能性も。結局、新しく紙の学習書を買わなければならない事態になることもあるでしょう。
また、タブレット端末は精密機器であるため、取り扱いにも注意が必要です。例えば、子どもがタブレットを落としたり濡らしたりして故障させた場合は、学習が一旦ストップしてしまいます。紛失の可能性は紙の学習書も同様ですが、故障の概念はタブレット特有のデメリットだといえるでしょう。
視力・姿勢・睡眠時間など身体的な問題が生じやすい
タブレット学習において注意したいのが、子どもの身体的な問題です。タブレット端末からはブルーライトが発生しており、睡眠の質の低下や眼精疲労を誘発します。眼精疲労は肩こりや頭痛などの副次的な身体トラブルを招き、子どもの健康を損ねかねないため注意が必要です。
また、夜中までタブレット端末を見ることで睡眠時間が遅くなってしまう可能性や、視力・姿勢が悪くなってしまうケースなどもあるでしょう。







