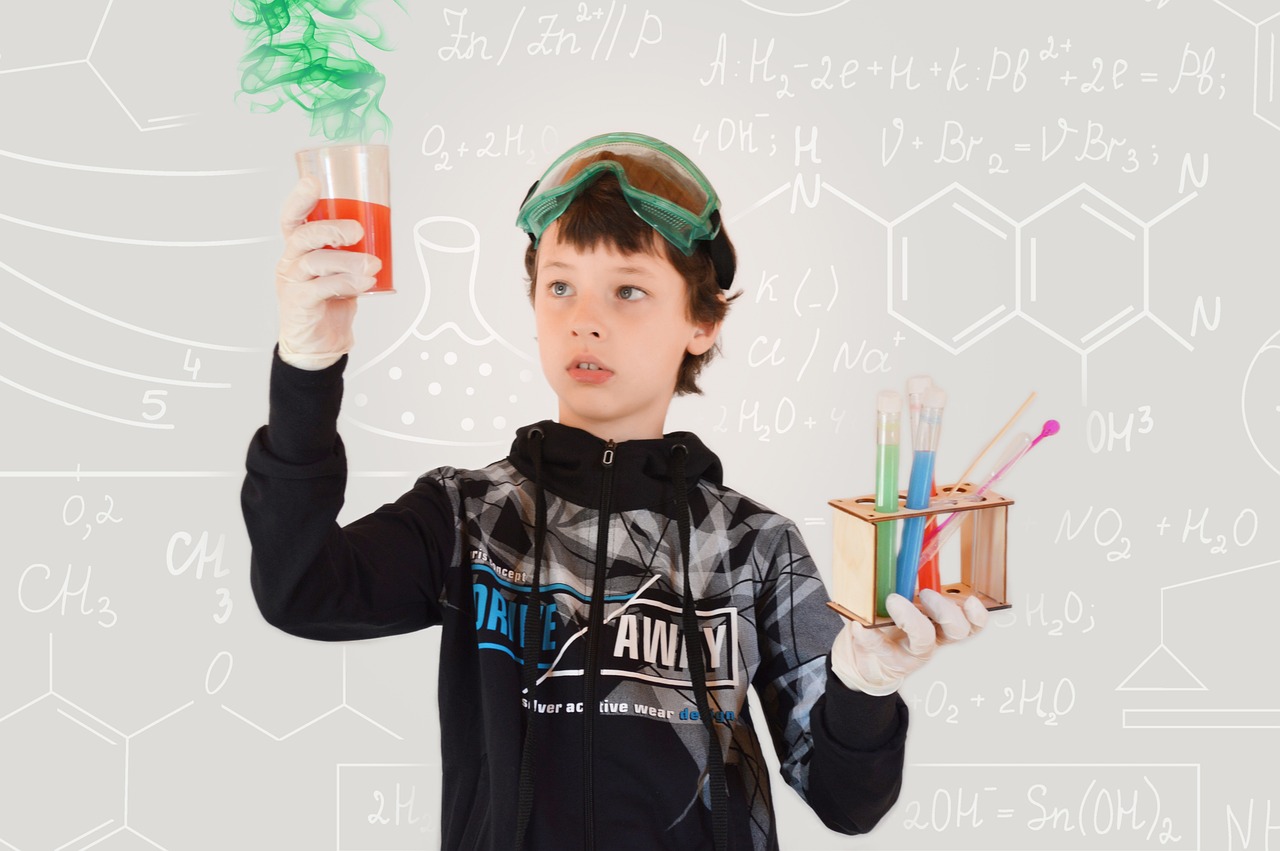【この記事の目次】
子どもを理系脳に育てたい!具体的な方法はある?

AIが発展している現代、職業の多くがAIによって変わっていくといわれています。親御さんのなかには、「将来子どもが生き抜くために理系思考を育てたい」と思う方もいるでしょう。
ただし、算数や理科よりも絵をかいたり詩を作ったりする方が好きな子どももいます。そのため、親が「理系脳の方がよい」と断言し、無理やり子どもに理系的な思考や行動を促す行為はよくありません。算数が苦手な子どもに叱咤しながら勉強させるような方法では、子どもはますます数字が嫌いになり、理系脳を育てられないでしょう。
そこで今回は、理系脳の特徴や文系脳との違い、理系思考の効果的な育て方などを紹介します。子どもの個性を大切にしながら、可能性を拓く視点で子育てしていきましょう。
理系脳の特徴
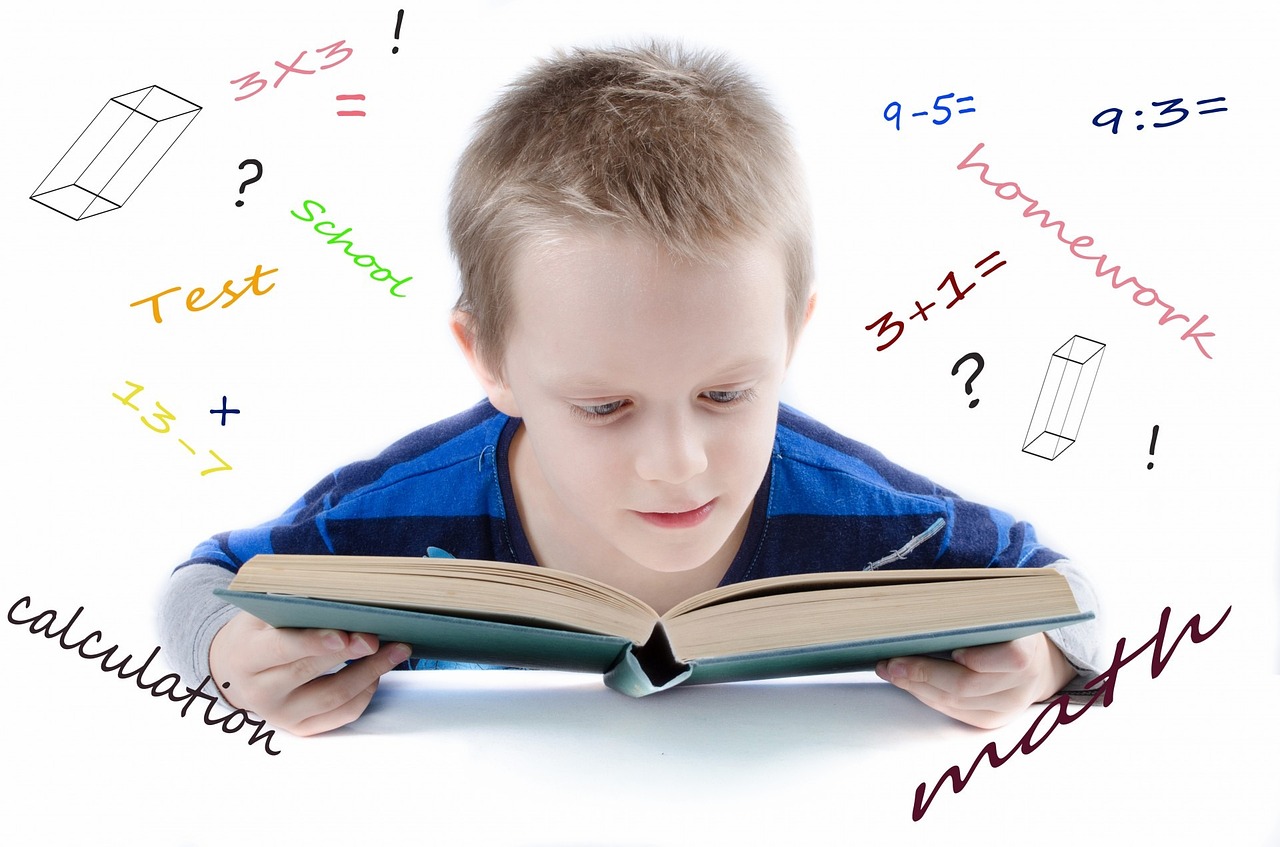
理系脳とは、物事を客観視する思考法を指します。たとえば、ある事象に対して数値やデータを用いて分析し、「〇〇であるのは▢▢が…となったからだ」などと結論づける考え方です。
理系脳の人は人間の五感や勘にあまり頼ることなく、数値やデータなどの客観的な情報を用いて証明や説明をするといえるでしょう。
ここでは、理系脳の特徴を3つに分けて解説します。
数値の正確さや客観的な根拠を重要視する
理系脳の人は「正確な数値であるかどうか」や「数値やデータで結果が示されているか」などを重視するため、「ただ何となく」といった表現や、脈絡のない会話などを好まない点が特徴です。
たとえば算数のテスト結果が88点であった場合、理系脳の子どもは次のような捉え方をします。
- 減点の12点はどこで引かれたのか?
- 作図で10点引かれたのはなぜか?
- 計算の2点は完全にミスか?
- 作図を改善すれば点数は上がるのか?
つまり、理系脳は結果にこだわり、その根拠を数値から見いだして改善点を洗い出す特性があるといえます。
物事を定量的に考える
「定量的」とは物事を数字に表すことを指し、抽象的な表現となる「定性的」とは区別されます。理系脳の人は、定量的に物事を捉える傾向にあります。
たとえば、降雨状況を他者に伝える場合、理系脳の人と文系脳の人とでは次のような違いが生まれるでしょう。
- 理系脳:昨夜は1時間に70mmの大雨だった
- 文系脳:昨夜は本当にたくさん雨が降った
理系脳の人は「たくさん」といった言葉で表現するのではなく、数値を使って具体的に表す点が特徴だといえます。
論理的思考力が高い
理系脳の人は、論理的思考力が高いという特徴を持っています。論理的思考力とは、物事の本質や仕組みを整理し、筋道を立てて考える能力を指します。
理系分野が得意であれば、論理的思考力を使って問題の解決方法などを導き出せるでしょう。この際、理系脳の人がよく用いるのが仮説立証で、要件やデータを収集したり客観的に分析したりしながら解決策をまとめます。
また、理系脳の人が解決策を説明する場合は、はじめに結論を述べてから結論に至る背景や流れを話す傾向にあります。こうした説明方法も、論理的思考力によるものだといえるでしょう。
理系脳の反対「文系脳」の特徴

理系脳の反対語としては、「文系脳」が挙げられます。理系脳があらゆる物事を客観視するのに対し、文系脳は物事を感情的に読み取る思考法といえます。
つまり、文系脳の子どもは言葉の意味を直観的に受け取る傾向にあり、理系脳の子のように言葉の背景を探る姿勢をあまり見せません。
理系脳をより深く理解するためには、文系脳の特徴も知っておく必要があるでしょう。ここでは、文系脳の特徴を3つ紹介します。
言葉の意味を深く捉える
文系脳の特徴である「言葉の意味を深く捉える」とは、言葉に込められた意図や目的、ニュアンスなどをすべて受け取ることを指します。
たとえば、子どもが友達から「それはダメだよ」といわれたとしましょう。理系の子どもは「どうして友達はダメといったのだろう」と言葉の背景を読み取ろうとします。
しかし、文系脳の子どもは理系脳の子どものように言葉を客観的には捉えません。「ダメ」という言葉が持つ「注意」や「禁止」といったニュアンスや、相手が「ダメ」といった際の気もちなどもそのまま受け止めようとするのです。
感情的な部分を読み取る
文系脳の場合、物事を感情的に受け取る傾向にあるといえます。理系脳が言葉や物事の背景に着目し、客観的に情報を得ようとするのとは対照的でしょう。
たとえば、友達から「この消しゴムいいね」といわれた場合、文系と理系の子どもとでは次のように対応が分かれます。
- 理系脳の子「少しの力で消せるし、大きさも丁度いいものだ」
- 文系脳の子「大好きな猫のイラストが描かれているの!かわいいでしょ?」
理系の子の場合は物の機能性や利便性を重視しますが、文系の子は自身の感情面を大事にする傾向にあります。
直観力が高い
文系脳の子どもは、理系脳の子どもと比べて直観力が高いという特徴があります。直観力とは、起こっている物事をそのまま感じ取る力のことです。
直観力が高い子どもは、既存の価値観や見方にとらわれず、「目の前のもの」に集中できます。直観力は五感と関連しており、他者や事象に左右されず、独自の視点を導き出すことにつながるでしょう。
そのため、何かを発明する際は文系的な思考があってこそ、新たな発見やアイデアを創出できると考えられます。
理系脳と文系脳の見分け方

理系脳と文系脳の見分け方に関して、参考までに下記の例を挙げます。子どもが理系脳なのか文系脳なのか知りたい場合に試してみましょう。
- 理系脳は「腕を組むと右手が上にくる」、「AAABBBCCCのような文字列を好む」
- 文系脳は「腕を組むと左手が上にくる」、「AMOVBIPWCのような文字列を好む」
腕組みの際に右手が上にくる場合が理系脳というのは、理数系でよく使う左脳が右半身をコントロールしていることによります。文字列については、理系脳が規則性を好みやすい点と関連しています。
文系脳の人が腕組みをすると左手が上にくる理由は、イメージや直感をつかさどる右脳が左半身をコントロールするためといえるでしょう。また、理系脳の人と異なり不規則な文字列を好むのが文系脳の人の特徴です。
このほか、「100円玉3枚をもって買い物に行きました。180円のものを買った場合、おつりはいくらでしょうか」といったような問題でも見分けられるでしょう。
- 120円と答えるのは理系脳
- 20円と答えるのは文系脳
理系脳は算数の問題として捉える傾向にあり、数字にもとづいて解答しますが、文系脳は実際の買い物を想定して「100円玉2枚を出せばいい」と判断します。
ただし、一概に「この子は〇〇脳だ」と断定しない方が、子どもの成長にプラスとなるでしょう。この点については、次章でくわしく解説します。
理系脳と文系脳に優劣はなし!子どもの能力を上手に引き出そう

AIが発達していく社会に対応するためには、理系思考である方が有利だと考えられています。しかし、理系脳と文系脳に優劣はなく、一方にかたよりすぎれば逆に生きづらくなるでしょう。
その理由は、人間それぞれに持って生まれた特性があるためです。算数や理科において能力を発揮する子どももいれば、文化や歴史などに興味をもつ子どももいます。
また、同じ植物を目にしても花の色に感動して絵で表現しようとする子もいれば、花びらの数をかぞえ始める子もいることでしょう。
親は子どもが理系脳か文系脳かと決めつけず、まずは子どもの能力や個性を大切にすることをおすすめします。その上で、子どもがどちらかといえば理系脳なのであれば、理系思考を伸ばしつつも文系的要素を補うサポートをするとよいでしょう。