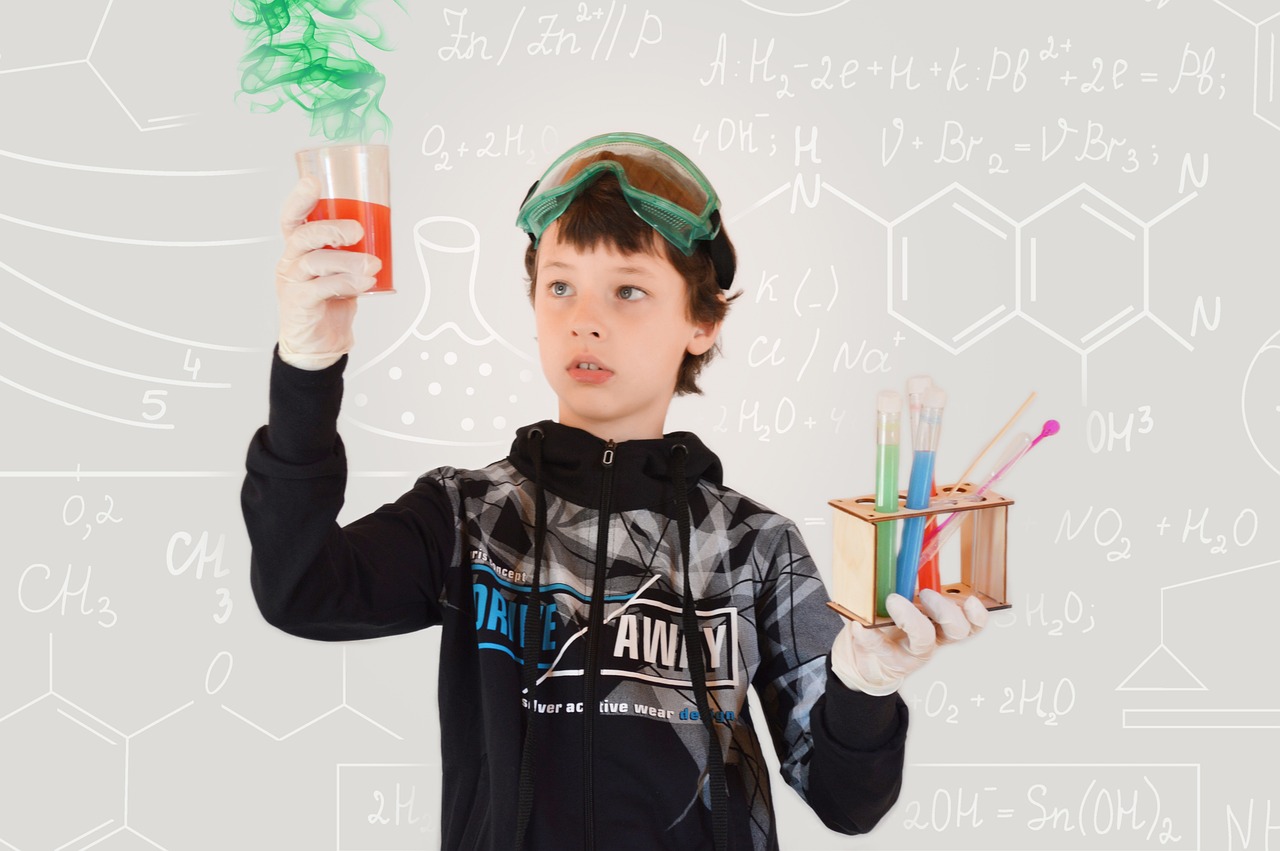子どもの理系脳を育てる方法

理系脳と文系脳に優劣はありませんが、論理的思考力があまりにも備わっていないと、せっかくのアイデアを形にできないことなどもあるでしょう。
予測不可能な時代を生きるためには、感覚や感性だけではなく、課題を設定して筋道を立てながら解決へ導く理系的な考え方が必要になります。
ここでは、子どもの感性を磨きつつ理系脳を育てる方法を6つ紹介します。
子どもが自発的に物事を考える機会を増やす
子どもが理系か文系かに関係なく、自発的に物事を考える機会を増やすことは大切です。その理由は、子どもの自発性がなければどちらの特性も十分に伸ばせないためです。
たとえば、子どものテスト結果が悪い場合、親が叱るだけでは子どもは問題として捉えません。
こういった場面では、「どうして結果が悪かったのだと思う?」と子どもに考えさせることが重要です。子どもはテスト内容をふり返り、どこがどうよくなかったのかを考え始めることでしょう。
子どもに説明してもらう機会を増やす
理系脳の特徴である論理的思考力は、生活の中で育てられます。親は何かと先回りして「〇〇は▢▢でしょ?」などと伝える傾向にありますが、そこをぐっとこらえて子どもに説明させましょう。
たとえば、子どもが学校の出来事を話すタイミングなどが、理系脳を育てるよい機会となります。子どもが「今日は楽しかった」と親に伝えたときは、「そう、よかったわね。どう楽しかったのかを教えてよ」などと促すのです。
説明するには話す内容や順番、根拠など多くの理系的要素が必要です。最初から完璧さを求めれば子どもは嫌がるため、少しずつ話に肉付けさせながら、説明する力を育てていきましょう。
親子で図鑑を楽しむ
図鑑にはさまざまな情報が掲載されており多くの発見があるため、親子で一緒に図鑑を楽しむのも理系脳を育てるのに有効な方法となります。
理系脳には、「客観的な根拠を重視する」といった特徴があります。図鑑を見る行為は「なぜ?」「どうして?」といった疑問をもたせやすく、子どもは好奇心を刺激されることでしょう。
さらに図鑑で生まれた疑問を調べるために、別の図鑑や書籍、インターネットなどを活用する方法も学べます。
生き物と触れ合う
理系脳を育てるには、生き物と触れ合うことも効果的です。理系脳は物事を客観的に捉える思考法であり、客観性を磨くには「観察力」がポイントとなります。
生き物を飼えば、環境を整えたり餌をあげたりするでしょう。その結果、自然に生き物の様子を観察し始めるようになり、動植物に対する興味関心をもつようにもなります。
また、生き物と触れ合うことは子どもの五感や好奇心を刺激し、感性を育てることにもつながります。
ブロック型の積み木で遊ぶ
知育玩具として親しまれているブロックは、理系脳を育てるうえで効果を発揮するとされています。その理由は、ブロック遊びによって理系脳の特徴である論理的思考力を育てられるためです。
論理的思考力とは、ある目的を達成するためのパーツを洗い出し、順番に組み立てる考え方を指します。ブロック遊びは造形に必要な「パーツ=ブロック」を組み合わせるため、まさに理系脳を育てるのに適した方法だといえるでしょう。
子どもと一緒に料理をする
ブロックと同じく料理もパーツの組み合わせで作られるため、理系脳を育てたい場合は、子どもと一緒に料理をするのもおすすめです。
料理のパーツは「材料」であり、それを組み合わせる「手順」を作業の中で学びます。また材料には「分量」があるため、分量を正しく計る必要性も生まれます。
つまり、料理には理系脳の特徴である「正確さ」「定量的」「論理的思考力」などの要素が盛り込まれているのです。親子で楽しみながら生活に役立つ力を身につけられるだけでなく、理系脳を育てられる方法だといえるでしょう。
理系脳の力はAIやITが発達する未来で役立つ

理系脳の力は、AIやITが発達し、予想を覆すようなサービスが生まれる時代において必要なものです。不測の事態に対応するには、あらかじめ問題に気づき論理的に解決していく理系的な思考が求められるでしょう。
理系脳に関連する力について簡単にまとめると、下記の通りになります。
- 観察する力
- 気づく力
- 定量的に分析する力
- 問題解決力
- 論理的思考力
予測が不可能な時代では、物事や事象のありのままを観察し、疑問や課題を発見する力が求められます。背景にある要因を抽出し情報を客観的に分析するのは、理系脳の得意な分野でしょう。
こうした理系脳の力に、言葉の意味を深く捉えたり直観的に考えたりする文系脳の力が掛け合わされれば、より深く考えスピーディに対応できる人間に成長していきます。
子どもの理系思考を養う習い事

理系脳の力を育てるには、普段の生活において子どもに考えさせたり理系脳につながる遊びをさせたりする必要があります。
ただし、各家庭でできることには限りがあるため、専門的な知識を身につけさせたい場合は理系思考を養えるとされる習い事をさせるのも効果的です。
ここでは、子どもの理系思考を養う習い事を4つ紹介します。
プログラミング
プログラミングとは、コンピュータを動かすために必要な構成を考え、パーツを組み立てていく作業を指します。作業そのものに論理的思考力が必要であるため、プログラミングは理系脳を育てるのに適しています。
「プログラミングは難しいのでは?」と思う親御さんは多いかもしれませんが、子どもが簡単に始められるプログラミング言語もあるため、意外に取りかかりやすいものです。
それでも難しさを感じる場合は、「パーツ」を扱うブロックなどで遊ばせて理系思考を育ててから始めることをおすすめします。
将棋
将棋の基本的な考え方である「駒得(こまどく)」は、理系的だといえます。駒得とは、取る駒と取られる駒の価値を比べて常に自分が得になるように進めることです。駒得により、たとえば次のような理系思考を養えるでしょう。
- 物事の筋道を立てて考える力
- ルールにしたがって先を読む力
- 状況を観察し分析する力
ほかに将棋を通して、理系脳に必要な集中力やねばり強さといった要素も育てられます。
麻雀
「〇〇を▢▢すれば勝てる」と予想する麻雀は、理系の特徴である論理的思考力を鍛える際に効果的です。
「麻雀を子どもにさせるのは抵抗がある」と考える親もいると思いますが、理系脳を育てるうえで役立つポイントは知っておきたいところです。
麻雀はいわば、「裏を読もうとするゲーム」で、見えないところで相手が何をどうしようとしているのかを考えます。そのほかのカードゲームなどにも裏をかく要素はありますが、麻雀はさらに複合的な「裏読み」が必要で、理系脳を鍛えるうえで役立つと考えられるでしょう。
そろばん
暗算力を養うとされるそろばんは、筆算とは異なる計算法を用いており、理系思考を育てるうえで効果があります。
筆算とそろばん式暗算とでは、次のような違いがあります。
- 筆算:脳の「数字を処理する部分」のみが刺激される
- そろばん式暗算:脳の「イメージを処理する部分」を同時に活用する
そろばん式暗算は脳を全体的に使うため、集中力や情報処理能力などが身につきます。つまり、そろばんは物事を整理し効率的に処理する力を磨けるため、理系思考を育てたい場合に効果があるといえるでしょう。
子どもの理系思考を育てるなら『Wonder Code』

子どもの理系脳を育てたい場合、理系脳の特徴である「正確さ」「客観性」「定量性」などの要素を意識し、論理的思考力を育てることを念頭におきましょう。
家庭で理系思考を育てたい時は、親がいつも先回りして子どもの話を遮ってしまうことはよくありません。自発的に説明させることを大切にすると、子どもは論理的に話したり物事を理解したりできるようになります。
『Wonder Code』では、理系脳を効果的に養うカリキュラムを組んでおり、お子さんが楽しみながらプログラミング的思考などを身につけられます。家庭外でも理系脳を育てたい親御さんは、ぜひお問い合わせまでお気軽にご連絡ください。