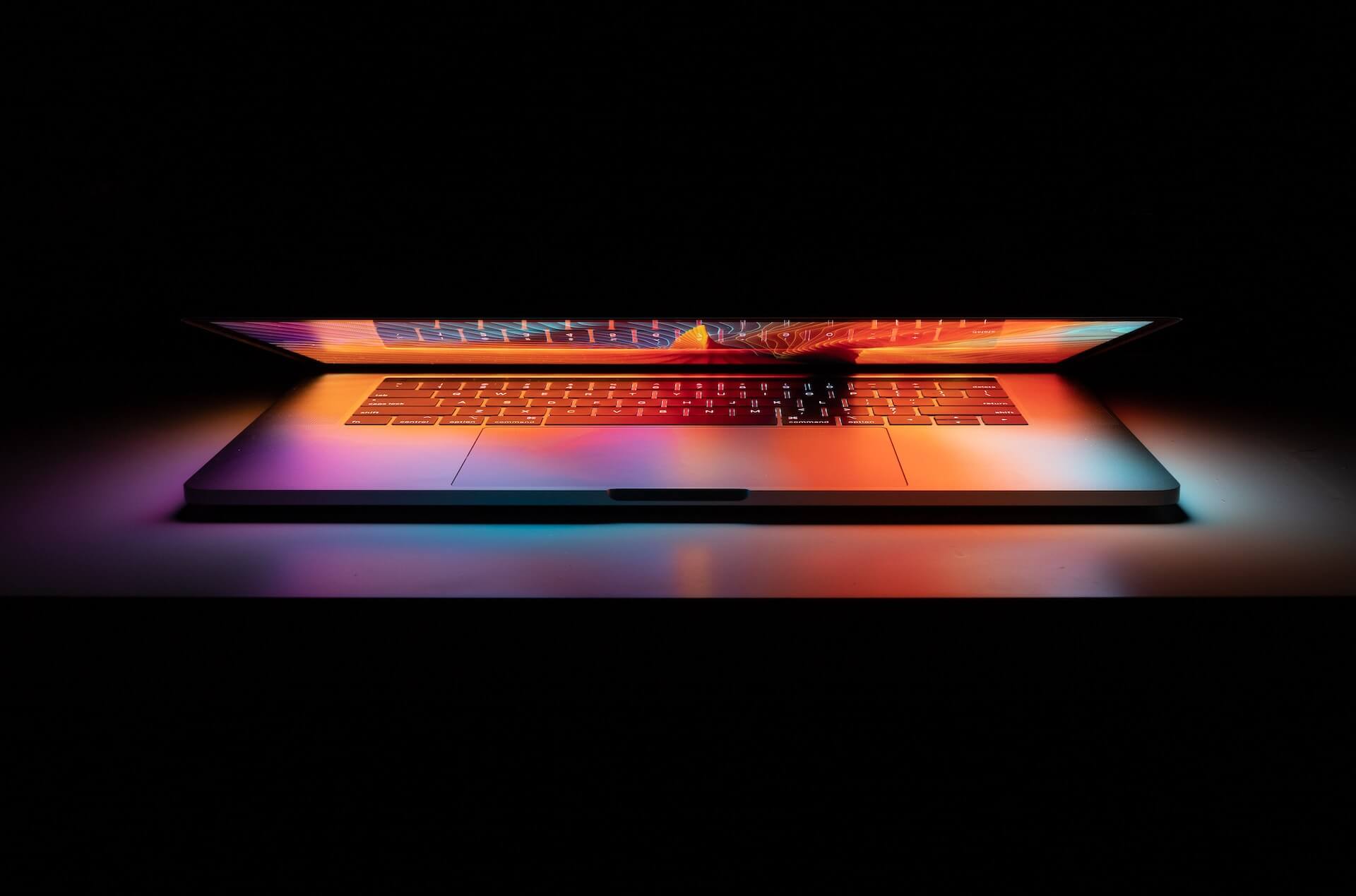子どもとITの距離感を縮める5つの方法

ここでは、子どもとITの距離感を縮める方法を5つご紹介します。子どもにとって、知的好奇心やワクワク感は最高の学習材料です。子どもの「楽しい」「おもしろい」という気持ちを引き出しつつ、将来的に役立つITスキルを養いましょう。
遊びやクリエイティブを通して、デジタルデバイスに慣れさせる
子どもとITの距離を縮めるためには、ITにポジティブなイメージを持ってもらうことが大切です。ITを用いた遊びやクリエイティブを通して、楽しくデジタルデバイスに慣れてもらいましょう。オンラインコミュニケーションを用いずに遊べるゲームでも構いません。
お絵描きソフトで好きな絵を描いたり、シンプルなDTMで作曲したりするなど、IT技術を介した自己表現を学ぶことでITがどんどん身近になります。パソコンやタブレットの設定を自分好みにカスタマイズしてもらう方法もおすすめです。
調べごとや学習をオンラインベースで行う
子どもの調べごとや学習は、オンラインベースで行いましょう。子どもに質問されてもすぐには回答せず「〇〇をやる方法って調べてみてごらん」や「今聞いたことをそのままパソコンに入力してごらん」などサポートするのがおすすめです。
動画・ブログ・SNSの投稿・ニュースなど、インターネット上に存在する数々の情報を自分で集めてもらいましょう。IT社会において、リサーチ力は重要なスキルです。日常的なリサーチや試行錯誤を通して、ITを上手に使いこなす能力を養いましょう。
プログラミングの学習を始める
子どもにITを身近に感じてもらうために、特におすすめの習いごとがプログラミングです。プログラミングでは、コードと呼ばれる「コンピューターに命令するためのデータ」を使いながら、思い通りに動作させるためのプロセスや技術を学びます。
子ども向けのプログラミング教室ではアニメーションやゲームなどを取り入れており、楽しみながらの学習が可能です。プログラミングで身につく論理的思考力や問題解決力は、あらゆる職業で役立つ能力であるため子どもの将来につながります。
ITにかかわる質問環境を用意する
子どもがITに触れる際は、ITに関する質問環境を用意することが大切です。たとえばプログラミングを学ぶ際は、学習過程でほぼ必ずエラーやバグに直面します。プロのエンジニアでさえも毎日のようにエラーと戦っており、その度にサイトや書籍で解決方法を検索します。
まだIT技術が身についていない子どもにとっては、解決方法をリサーチすることすら一苦労です。オンライン・オフラインにかかわらず、わからないことをいつでも質問・解決できる環境を整備しましょう。SNSの活用や匿名の質問掲示板なども一つの手段です。
デジタル技術を通して自己発信を行う
子どもにITを身近に感じてもらうためには、デジタル技術を通して自己発信しましょう。自己発信の例としては、ブログ・SNS・絵・音楽・動画・音声配信などが挙げられます。デジタルを介した自己発信ではITの楽しさを伝えられると同時に、インターネットリテラシーの教育ができる機会でもあります。
写真を含め自分のプライベートな情報を公開しないことや、自己発信することのリスクを伝えた上で、楽しみながら継続できる環境を整えましょう。特にブログやSNSは、スマートフォンだけで手軽に継続できるIT活動といえます。
楽しくIT技術を学ぶなら『Wonder Code』

今回は、ITの意味や子どもにITと触れてもらう方法などをご紹介しました。生まれたときからスマートフォンやパソコンが身近だった子どもにとって、ITはすでに生活の一部です。ただし、より深くITを理解するためには意識的な学習が求められます。
「遊びや学習以外にもITの用途がある」「自分たちの生活はITによって支えられている」と理解することで、ITとの距離感をさらに縮められるわけです。子どもの興味や関心に寄り添いながら、社会とITの関連性を伝えていきましょう。
Wonder Codeは、ロボットやプログラミングを通して楽しくITを学べる習いごとです。子どもの知的好奇心を刺激するメソッドを取り入れており、主体性のある学習をかなえます。
「子どもにITを身近に感じてもらいたい」と思っている人は、ぜひこの機会に無料体験教室や資料請求から始めてみてはいかがでしょうか。