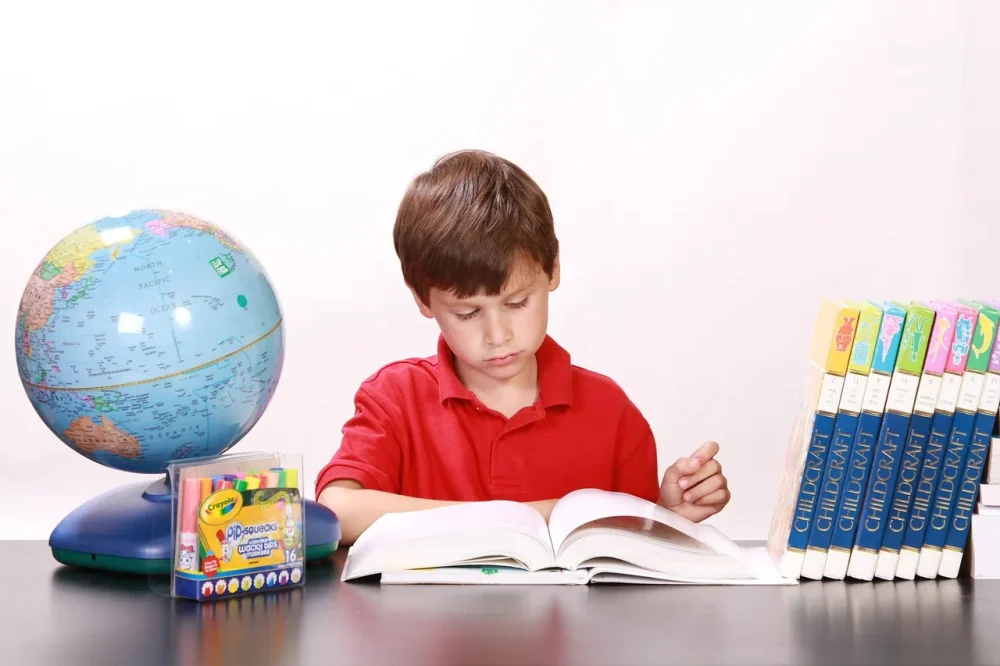子どもに毎日勉強してほしい…どうすれば学習が習慣化するの?

小学生から学習習慣を身につけるのは、将来に向けて学び続ける姿勢と自己成長を可能にするための重要なステップです。
しかし、保護者にとって「子どもがなかなか勉強しようとしない」「宿題以外の勉強にまったく関心がない」といった悩みは少なくありません。
そこで今回は、子どもに学習習慣を身につけさせる具体的な方法を紹介します。家庭で実践できる方法を取り入れて、子どもが勉強する習慣を育てていきましょう。
まずは、子どもがなかなか勉強に向かえない理由について解説します。
子どもがなかなか勉強に着手できない6つの理由
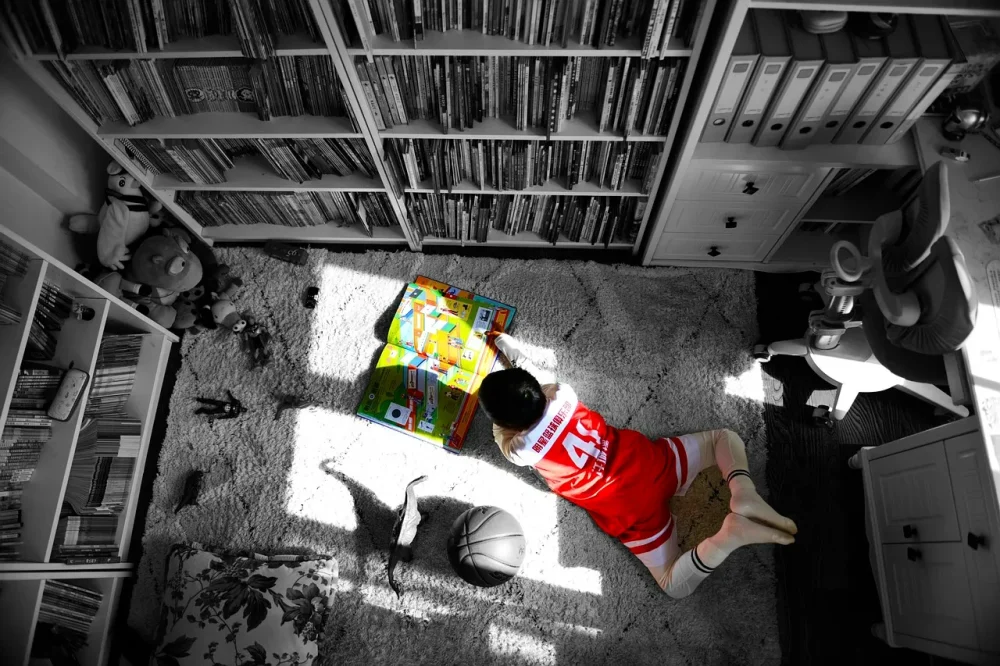
子どもが勉強に取りかかれない背景にはさまざまな要因があります。子どもに勉強を習慣化させるには、勉強に着手できない理由を把握し、家庭で支援する際のポイントを明確にしなければなりません。
ここでは、子どもが勉強にとりかかれない理由を6つ紹介します。今後のサポートにお役立てください。
友達や娯楽など、誘惑に弱い
子どもは友達や娯楽に引かれやすい傾向にあります。友達との遊びや娯楽は、即時的な楽しさや社交的な交流をもたらします。それに対して勉強は努力や忍耐が必要であり、すぐに成果が得られるわけではありません。
そのため、子どもは友達との遊びやスマートフォン、テレビなどの娯楽に魅力を感じる一方で、勉強に対して「難しい」「面倒くさい」といったネガティブな印象を抱きやすくなるのです。
勉強による成功体験が得られていない
成功体験とは、子どもが学習の過程で目標を達成し成果を上げることです。また成功体験は、子どもの自己肯定感やモチベーションの向上に重要な役割を果たします。勉強に関していえば、難しい問題を解決したりテストで高得点を取ったりする経験です。
もし勉強で成功体験を積んでいない場合、勉強が難しいと感じて挫折や失敗を恐れるようになるかもしれません。その結果、子どもは自分の能力や成果に対して自信を失い、勉強に対する意欲を低下させてしまう可能性があります。
勉強しないことによるデメリットに重大性を感じていない
一部の子どもは、勉強しないことによるデメリットを感じていない場合があります。子どもは今が楽しいと、将来のデメリットまで考えられないのかもしれません。
たとえば、ゲームの好きな子どもが勉強もせずに長時間ゲームをしていれば、娯楽追求の習慣が定着してしまい、ますます勉強に向かえなくなるでしょう。はじめは将来的なデメリットを自覚していたとしても、ゲームし続けることで次第に「今が楽しければいい」といった感覚に陥ってしまうのです。
勉強ができない自分を直視することがつらい
勉強が苦手な子どもは、自分の限界や弱点を直視するのがつらく、逃げたり嫌がったりする傾向にあります。こうした子どもにとって、勉強の難しさや成績の低さは自己評価を低下させる要素となるでしょう。
周囲から成績が悪い点を指摘されるばかりで、適切なサポートを受けられなければますます勉強に向かえません。また、たとえ自分では努力していても、学習に対して弊害や困難さを強く感じる場合も自己評価の低下につながるのです。
勉強する目的がわからず、モチベーションが湧かない
勉強の目的や将来の意義がわからないと、学習に対するモチベーションが上がりません。子どもは目的が明確であればあるほどやる気が出ますが「なぜ勉強するのか」がわからなければ、勉強に向かうことができないものです。
子どもに勉強する目的を理解させようとしても、子どもは「自分の好きなことや、将来何になりたいのか」がわからないのかもしれません。勉強する目的だけでなく、子ども自身が自分の好きなことやしたいことを明確にできない場合も、勉強に対するモチベーションを低下させます。
体や心の状態に余裕がない
子どもが疲れていたり心に不安があったりすると、勉強に集中できない場合があります。また長時間の学習やストレスによる心の負担は、学習意欲や成績に悪影響を及ぼします。
心や体が疲れているときは、勉強に取り組むこと自体が苦痛に感じられるはずです。そのため、集中力や注意力が低下し、知識を吸収したり記憶したりするのが困難になるでしょう。また、心にある不安やストレスが頭から離れないため、勉強に集中できないと考えられます。
勉強を習慣化できないままだとどうなる?

子どもがなかなか勉強に集中できない背景には、さまざまな要因があることがわかりました。要因を取り除いたり改善したりしなければ、子どもはなかなか勉強に集中できません。
ここでは、勉強の習慣化が達成されない場合のリスクについて解説します。
学年が上がるごとに、どんどん勉強についていけなくなる
勉強を習慣化させられない場合、学年が上がるごとに勉強についていけなくなるリスクが高まります。その理由は学習には系統性があり、基本的な内容が理解できなければ次のステップに進みにくいためです。
子ども自身が学習の遅れを感じてストレスを抱えるようになれば勉強に集中できず、当該学年に必要なスキルや知識を定着させられません。進級するたびに学習内容が増えるため、次第に太刀打ちできなくなり勉強嫌いが加速してしまうでしょう。
自分に自信を持てなくなる
勉強の習慣が身につかないままでいると、子どもは自分に対する自信を持てなくなります。勉強になかなか取り組めない自分に不安を感じ、実際の成績が悪ければ自己評価が低下する結果となるでしょう。
また、自信を持てない状態では、他人の評価に過度に依存しやすくなります。友達の成績と比較して自分の成績の低さを気にしたり、「自分はダメだ」といった自己卑下の感情を抱いたりするのです。自己肯定感を築くことが難しくなり、自信を持てないまま大人になってしまうでしょう。
将来の選択肢やキャリアの幅が狭まる
勉強は知識やスキルの習得、そして自己成長を促進するための重要な要素です。勉強を通じて課題解決能力や論理的思考力、情報処理能力など、さまざまな能力を身につけられます。
これらの能力は将来の職業や分野において基盤となるものであり、キャリアのチャンスを広げる要素となります。勉強の習慣がないままでは、職場や社会で学習の機会を逃したり、自己成長を促したりするのが難しくなるでしょう。