子どもが小学生になったら、習い事に通わせるべき?
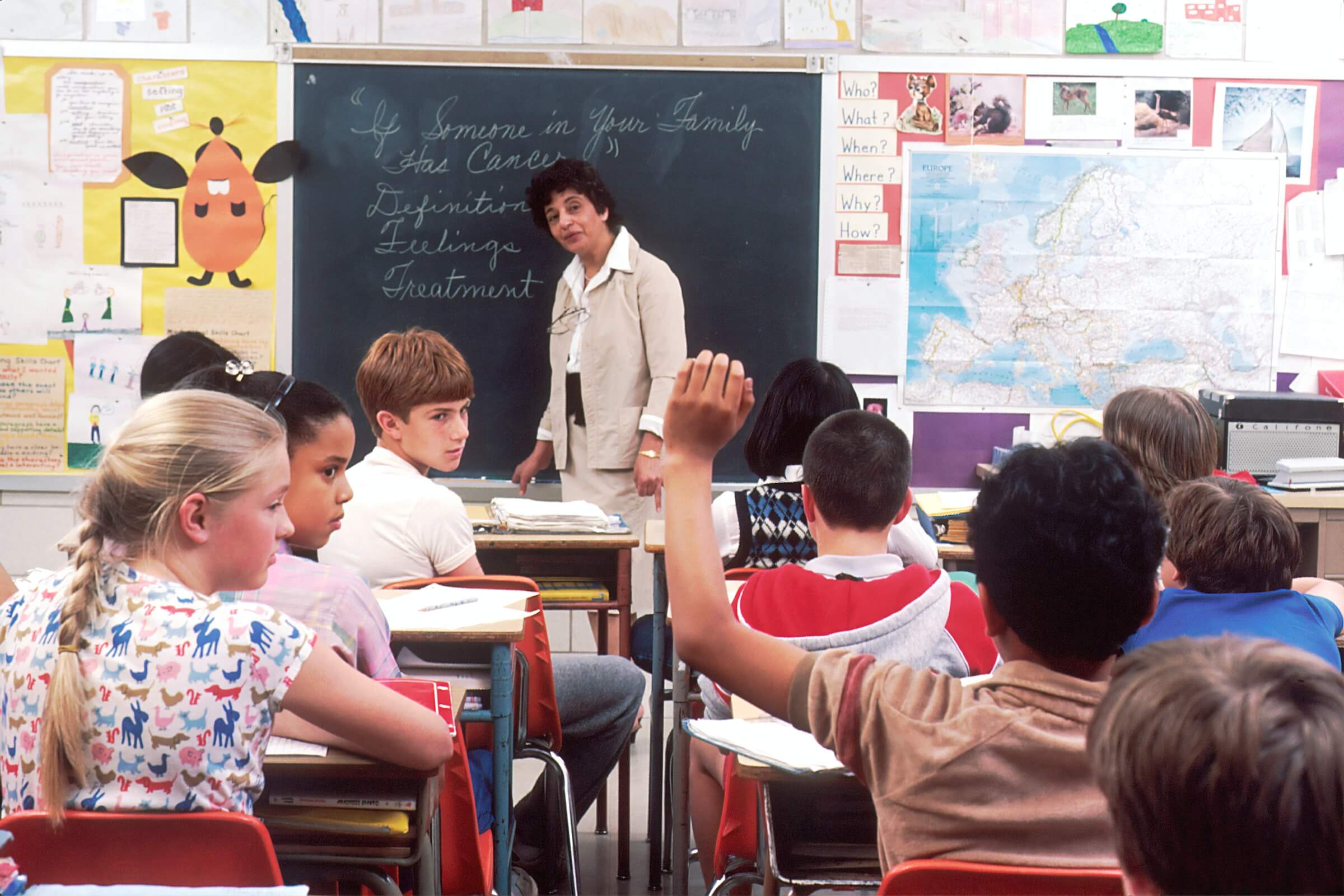
子どもが小学生になると興味関心の幅が広がるため、習い事に通いたい子どもが増えてくるのではないでしょうか。小学校から帰宅後、家で遊んでばかりいるより習い事をしてスキルを身につけさせた方が良いのでは?と感じる保護者もいるでしょう。
厚生労働省の調査によると、小学1年生〜3年生で習い事をしている割合は8割以上と、多くの子ども達が習い事をしている結果に。習い事は技術を体得するだけでなく、家庭や学校以外での人間関係を構築したり、努力の大切さを学んだりできる場でもあります。子どもや保護者の意向・金銭面を吟味して習い事を前向きに考えてみるのも良いでしょう。
ただし良さそうな習い事があるからといって、増やしすぎると逆効果になる恐れもあるため注意が必要です。
今回は「小学生の習い事の数」や「習い事が多すぎることで生じるデメリット」について解説します。
子どもにとって最適な習い事を厳選し、将来役に立つスキルを手に入れましょう。
小学生の習い事はいくつまで?
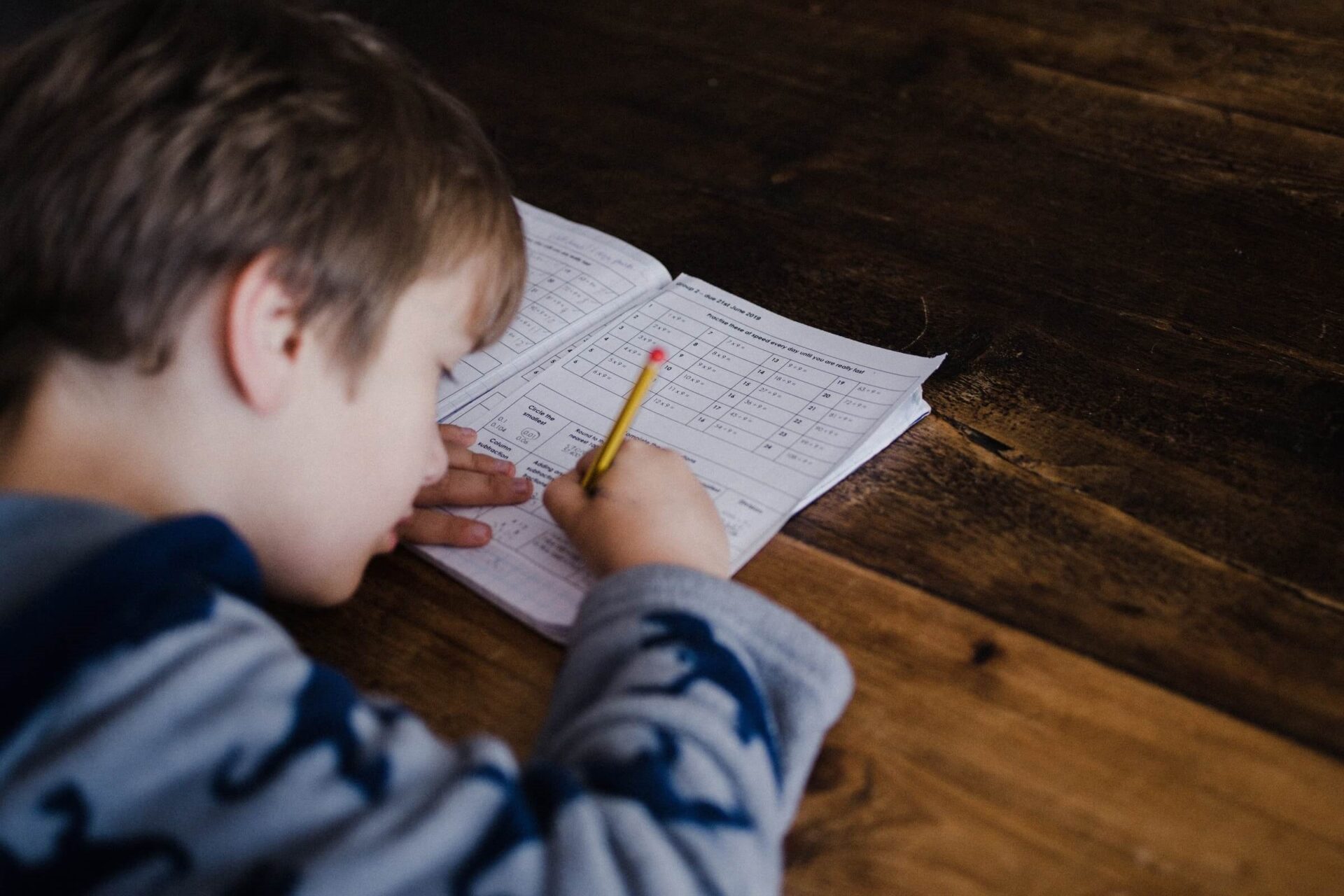
小学生の習い事のかけもちは、多くても3つ程度にとどめておくと良いでしょう。
小学生になると、さまざまな習い事に興味を持つ子どもも多いのではないでしょうか。せっかく興味を持ったのなら通わせてあげたいものの、習い事の数が増えてくると「そんなにやって大丈夫?」と不安に感じる方もいるはずです。
習い事に関するアンケートによると、6〜8歳では習い事の数は2つが39%と最多で、ついで3つが26%という結果でした。2つ以上習い事をしている子どもが全体の65%を占めていることから、習い事のかけもちは珍しくないようです。
ただし3個以上に増えてしまうと、費用がかさんだり時間的拘束が生じたりするため、子どもも保護者も疲弊してしまうかもしれません。
参考:アクトインディ株式会社いこーよ「2019年 習い事に関するアンケート」
習い事が与えてくれるメリット

習い事が小学生に与えてくれるメリットについて解説します。
早い子どもだと3歳くらいから習い事を始め、小学生になると習い事をかけもちする子どもも珍しくありません。多くの子どもが通っている習い事には、どんなメリットがあるのでしょうか。
この章では、習い事が与えてくれるメリットを3つ紹介します。
人生を豊かにするための知識やスキルが身につく
習い事をすると、知識やスキルが身につき人生を豊かにできるでしょう。
習い事には、運動系・芸術系・学習系などさまざまな種類があります。どの習い事も、子ども自身が前向きに取り組み身につけることで、一生役に立つスキルを手に入れられます。
どんな教養があっても、その教養を生かして将来の仕事につなげられるかは子ども次第です。しかし教養がなければ目指すことも生かすこともできません。学校や習い事を通じて得た教養は、子どもの未来の可能性を広げ、より豊かにすることが期待できるのです。
学校や家庭だけではわからない価値観に触れられる
習い事をすれば、学校や家庭だけではわからない価値観に触れられるのがメリットです。
習い事をすることで、子どもは自分とは違う人たちと出会う機会が増えます。習い事の先生や仲間、対戦相手などは、子どもの普段の生活圏にはいない人たちかもしれません。習い事を通した人間関係の中で、普段の生活では知り得なかった多様な価値観や視点を知れるでしょう。
多様性を知ることは、子どもの人間形成にとって大切です。自分以外の人たちの存在や考え方を尊重し、理解しようとする姿勢が育つでしょう。そして他社理解は、グローバル化が進む現代社会で必要な能力でもあるのです。
自分らしさや個性を獲得できる
習い事によって、子どもが自分らしさや個性を獲得できます。
子どもは、習い事を通じて関連する技能を身につけるわけです。学校において、その技能はその子独自の特技として認知されます。また、自分が得意なことに対して自信を持つきっかけにもなるでしょう。
また夢中で習い事に取り組む中で、自分の思いを伝えたり、他者と相談したりする機会もあります。さまざまな習い事でのコミュニケーションは、自分らしさを見つけるチャンスでもあるのです。
小学生の習い事が多すぎることによるデメリット

小学生が習い事をすると、スキルが身につくなどの利点がある一方で、習い事が多すぎるのも注意が必要です。
習い事を増やしすぎることで、次のデメリットが生じます。
- 本業が疎かになりやすい
- 自由に過ごせる時間が減る
- 一つひとつの習い事の質が落ちやすい
- 子どもだけではなく、保護者も疲弊しやすい
それでは1つずつ解説していきます。
本業が疎かになりやすい
小学生が習い事を増やしすぎると、本業である学校の勉強が疎かになる可能性があります。
小学校の勉強内容は、一定水準の学習を受けられるように学習指導要領に従って策定されています。習い事が多すぎると学校の宿題ができなかったり、疲れて授業中に集中できなかったりすることもつながりかねません。
習い事は子どもの才能や興味を伸ばすための一つの方法です。しかし、習い事を増やしすぎることで子どもの将来に必要な小学校での学びが疎かにならないよう注意しましょう。
自由に過ごせる時間が減る
習い事を増やしすぎるデメリットとして、子どもが自由に過ごす時間が減ることがあげられます。
習い事は、実施している時間だけでなく、前後の移動時間・自主練習のための時間などが多くの時間が必要です。習い事の数を増やせば、その分習い事に関連する時間を捻出する必要があるため、自由な時間が減ることを覚悟しなくてはなりません。
自由な時間が減れば、友達と遊んだり家族で過ごしたりするのも難しくなります。またデフォルトモードネットワーク(DMN)と呼ばれる、記憶のつなぎあわせやひらめきに影響を与える可能性がある脳領域は、のんびりしている時間に活発になると言われています。自由に過ごす時間が減れば、DMNが活性化しづらくなる可能性もあるのです。
一つひとつの習い事の質が落ちやすい
小学生が習い事を増やしすぎると、一つひとつの習い事の質が落ちやすいデメリットがあります。
習い事はその時間だけやっても上達しないものが多い傾向です。例えば、サッカーやピアノ、塾などは自宅での練習や学習を毎日積み重ねることで上達します。
習い事の数が多ければ、それぞれの習い事に対して自主的な練習が必要になるのです。その上、小学生には小学校の宿題もあります。習い事の種類が多くなると、一つひとつにかけられる時間が少なくなるため、上達が難しくなる可能性も。結果的に、習い事の質が落ちやすいと考えられるのです。
子どもだけではなく、保護者も疲弊しやすい
増やしすぎた習い事は、子どもだけでなく保護者を疲弊させてしまいます。
というのも、習い事によっては、保護者の送迎や当番が必須な場合があるわけです。例えばサッカーや野球など、スポーツ系の習い事は、当番制になっていることが多い傾向にあります。保護者の負担になる習い事が増えれば、時間的・体力的に疲弊してしまうでしょう。
また、習い事には費用がかかります。月謝だけでなくユニフォームや関連物品などにも費用が必要です。習い事を増やすと金銭的な負担が重くなります。







